「ボンドさん、失意の男というのは、じわじわとやられていくものなのですよ」
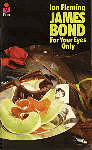 ナッソーの夜 ナッソーの夜
はじめに
「私は小説家でなく物書きなんだ」フレミングは自分のことを指してこういっていた。退屈な電車の中やひまな時にでも読み捨てられるようにと・・・。謙遜と自嘲が入り混じったことばである。たとえばレイモンド・チャンドラーが詩人になるためのステップとして書いた探偵小説が本流になってしまったように、ボンドで有名になってやりたいことができる土壌を作りたかったのが、フレミング=ボンドのイメージが出来上がってしまったため、身動きが取れなくなってしまったのではと思ったりする。
ほんとうのところフレミングは彼の言うところの「小説家」になりたかったのではないだろうか。
一小説だと発表の場は与えられることはないけれども、みんなが欲しがるボンドをどこかに出せばどんなことでもできるに違いない。そういった思惑の一編だろう。
ボンドシリーズでは一番退屈で最低なものかもしれないが、一文学作品としてくくられる物としてみると、俗物的な描写が未練として残っている「珍魚ヒルデブラント」より洗練されたものになっている。
ストーリィ
マイアミへ向かう前夜、あまり会いたくないジャマイカ総督との時間を過ごさなければならない夜、たまたまボンドの「結婚するなら、エア・ホステスか日本人がいい」という言葉から、提督はエアホステスと結婚した友人フィリップ・マスターズの話をする。
妻の裏切りによってじわじわと壊されていく様、破滅させられても敗北を認めず、じっくりと正確に復讐を組み立てていく男。
総督はそれを慰藉の量の法則と呼んだ。男女には何らかの基本的人間性が通じている限りその関係は続きことができる。しかしどちらかが、相手が生きようが死のうが関係ないと本気で考え出したらお手上げだと。
この感情は自我にに対する屈辱、自己保存の本能が危機にさらされた時現れる。自己の存在の危機にさらされた時に現れてくる残忍性である。妻が慰藉の量を少しでも与えていたら、彼はここまでやらなかったろう。
その完璧すぎる復讐にボンドは図らずも相手の女性に同情してしまう。
しかし復讐とは元来そういうもので、ボンドがいる諜報の世界は、国単位で復讐の繰り返しを行っている世界なのだ。だがそんなものも感情かなまに出ている人間喜劇にくらべたら他愛のないものなのかもしれない。
|